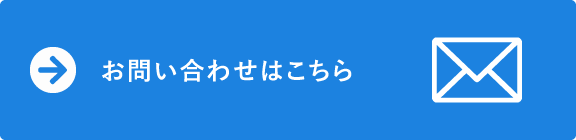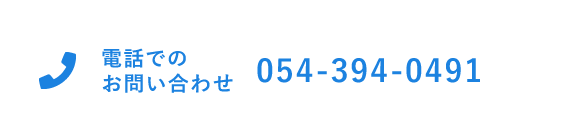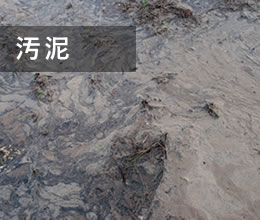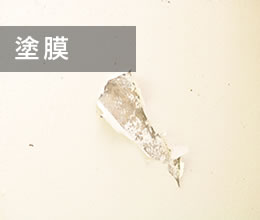土壌汚染の調査について
土壌汚染対策法は、「土壌汚染の状況を把握し、人の健康被害に対する防止・対策・措置を実施することによって、国民の健康を保護すること」を目的として、2002年5月に制定されました。土壌汚染の調査は、土壌汚染対策法や各都道府県条例による法定調査、土地売買、賃借、土地資産評価などの理由で自主的に調査する自主調査のケースがあります。法施行と環境保全の意識も高まり、調査の数は着実に増えています。
土壌汚染に関する調査・分析は、土壌汚染対策法、都道府県条例、建設発生土受入基準、土壌環境基準、及び土地の売買時の確認調査等に基づき行います。
土壌対策汚染法、静岡県盛土条例、海防法等の分析項目に対応できます。
ご相談ください。

土壌汚染対策法の法定調査
土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染状況の調査を行わなければならないケースは、主に以下のような場合があります。
特定有害物質を取り扱っていた施設が廃止された場合
土壌汚染の原因となり得る特定有害物質を取り扱っていた施設が廃止された場合、その土地の所有者や管理者は、汚染の有無を確認するために土壌汚染状況調査を行う義務があります。
例:化学工場、印刷工場、メッキ工場など

土地の形質変更を行う場合
3,000㎡以上の土地の形質変更で、掘削する面積+盛り土する面積≧3,000㎡の場合
例:土地開発・建設など

行政からの命令があった場合
自治体や国などの行政機関から調査命令が出された場合、土地の所有者や管理者は、その指示に従って土壌汚染の調査を行わなければなりません。

※都道府県によっては、土壌汚染対策法とは別に条例で義務調査の命令が発せられる場合があります。
個別の案件については、お気軽に弊社へお問い合わせください。
分析項目について
| 分類 | 分析項目 |
|---|---|
| 第一種特定有害物質 揮発性有機化合物 (12項目) |
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン |
| 第二種特定有害物質 重金属等 (溶出10項目) (含有9項目) |
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、アルキル水銀化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物 |
| 第三種特定有害物質 農薬等 (5項目) |
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機燐化合物 |
静岡県盛土条例項目にも対応できます。
建設発生土の土壌調査
近年、建設発生土(残土)は再資源(埋立や盛土の材料など)として有効利用されています。そのため各地方自治体では建設発生土について独自の条例や指導要領、ガイドラインを制定しています。また、建設発生土の処理場にも受入れ基準が設けられております。
静岡県盛土等の規制に関する条例
令和3年7月に熱海市の土石流災害が発生し、二度と同様の災害を発生させないために、盛土等の規制を図るために制定したものです。大まかに下記について調査を行うことが義務付けられています。
盛土用地の土壌調査 搬出前の土壌調査 盛土後の定期的な土壌・水質調査

残土処理場の受入基準
建設発生土を受入施設へ運搬する場合は、受入れ前に受入基準に適合しているか確認する必要があります。
受入施設の残土処理場へ搬入する前の土壌調査 他の土地で再利用する前の土壌調査

海洋汚染及び海上災害の防止法に関する法令
海洋投入処分を行う場合は、土壌調査を行うことが求められています。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項の項目

静岡県盛土条例に対応した項
| 分類 | 分析項目 |
|---|---|
| 溶出量試験(28項目) | カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン |
| 含有量試験(11項目) | カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素、銅(農用地)、ダイオキシン類 |
※自治体及び受入施設の仕様に応じた分析に対応しますので、お気軽にご相談ください。
土地売買等に伴う任意での土壌調査
土壌汚染対策法では、特定有害物質の使用届けがなく、対象地の総面積が3,000㎡以下の場合、土壌調査の義務が発生しません。しかし、現在は土地売買、賃借、土地資産評価などの理由で、土壌調査を任意で実施することが増えています。実際、特定有害物質の使用が無かった土地にであっても、建築する際に持ち込んだ盛土等に汚染物質が混入していると考えられるケースの汚染が確認されています。
汚染された土地を知らずに売買し、後々問題とならないようにするために、任意での土壌調査を行うことをおすすめします。
自主調査の例

土地を売る

土地を買う

土地資産評価

畑の土を調べたい

土地担保に融資を受ける

ガソリンスタンドの売却
買った土地に土壌汚染があった場合に、その除去費用が膨大になることがあり、土地の価値が大きく下落するリスクがあるため、特に工場跡地等では、買主から売買の際に土壌汚染調査を要求されるケースが増えています。
例えば、クリーニング店では、テトラクロロエチレン(パークレン)は使っておらず、石油系溶剤のターペンを使用していても、テトラクロロエチレンの汚染の可能性を払拭するために調査するケースがあります。
自主調査を行うことで、事前にリスクを把握し、適切な対策を講じることができるため、後々の法的問題や費用負担を避けることができます。
郵送いただいた土壌サンプルを分析します。
お客様自身で土壌サンプルを採取していただき、郵送していただいた検体を分析するサービスもご提供しています。また、分析項目によっては事前に当社にて専用容器及び採取器具をご用意させていただくことも可能です。
※土壌の採取は法律によって定められている場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
詳しくは「郵送で対応できる調査・分析」をご覧ください。
産業廃棄物分析
汚泥、燃え殻、ばいじん、廃油、廃酸、廃アルカリ等の産業廃棄物などについて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」では、特別管理産業廃棄物の判定基準が定められており、分析実施項目、基準値等も定められております。
「廃棄物処理法」により事業活動に伴って生じた産業廃棄物を
「自らの責任において適正に処理」する義務があります。

産業廃棄物の種類
廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート、陶磁器くず、がれき類、ばいじん
主な分析項目一覧
- アルキル水銀化合物
- 鉛又は化合物
- 六価クロム化合物
- セレン又はその化合物
- シアン化合物
- PCB
- シマジン
- 水銀又はその化合物
- カドミウム又はその化合物
- 砒素又はその化合物
- ベンゼン
- チオベンカルブ
- ダイオキシン類
※上記以外の分析にも対応しています。詳しくはお問い合わせください。
各地の処分場は管轄の行政の指導のもと、基準を満たした産廃のみを受け入れるようにしています。そのため、処分場に産業廃棄物を持ち込む場合、有害物質が基準値以内である証明が必要になります。そのために産業廃棄物の分析が必要になります。
郵送いただいた廃棄物を分析します。
お客様自身で廃棄物サンプルを採取していただき、郵送していただいた検体を分析するサービスもご提供しています。また、分析項目によっては事前に当社にて専用容器及び採取器具をご用意させていただくことも可能です。
詳しくは「郵送で対応できる調査・分析」をご覧ください。